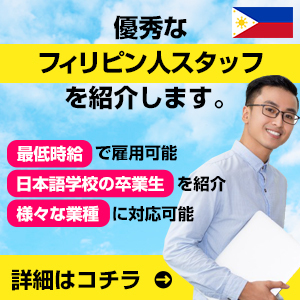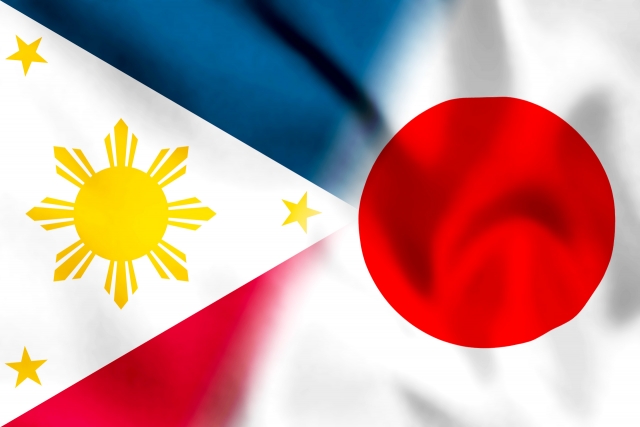2019年の4月より、改正された入管法による特定技能1号、2号という新しい在留資格の運用が開始されました。
この在留資格は、外国人労働者にとって就労を目的とするための在留資格となり、今まで技能実習や留学の在留資格で来日していた人も、特定技能の在留資格を取得することにより、日本で労働者として働くことができます。
それ以前からも、日本での就労を目的とした在留資格に、高度人材に関するものがありますが、こちらは取得に厳しい要件があり、簡単に取得することができないものとなっております。
今回は、フィリピンからの就労者における特定技能や高度人材を取得するための要件、それらの就労のための在留資格と技能実習生との違いについて考えていきます。
フィリピン人による特定技能の取得
特定技能の在留資格を取得できる国は現在のところ、9か国が閣議決定により取得可能となる予定です。
その中でもフィリピンは、特定技能の在留資格を取得するための試験を、国内外で初めて行われたこともあり、政府としても注目している労働者受け入れ国となります。
初めて行われた在留資格に関する試験は、介護分野のもので、他の分野の労働に関する試験は今後、日本国内やフィリピン国内で行われていく模様です。
この部分は、あまり前例のない在留資格となるため、まだまだ手探りの部分がある感はぬぐい切れませんが、この試験の応募に数時間で定員となるなど、在留資格に対するフィリピン国内での注目の高さがうかがえます。
フィリピンの高度人材、EPAによる人材受け入れ

介護に関する特定技能の試験がフィリピンで初めて行われた背景には、EPAによる介護士、看護師候補の人材受け入れがあります。
介護分野では外国人技能実習生とは別枠で、介護士候補として介護施設などで就労する在留資格がフィリピンでは取得することが可能です。
これによって年間約50人程度のフィリピン人が看護師や介護士候補として入国しています。
こうした背景があることから、介護職の分野における特定技能の在留資格試験をフィリピンで実施したものと考えられます。
介護や看護の人材としては、フィリピンは他の国よりも就労の在留資格を取得しやすいという事情があります。
EPAによる人材受け入れでは、入国後、看護師や介護福祉士の国家資格を取得すれば、永住権が与えられるということが大きな特徴となります。
一方で高度人材については、通訳や技術者、大学教授などの日本でも頭脳労働を行うような人たちに該当する在留資格となり、取得要件が厳しくなります。
フィリピンも他の発展途上国と同様でこの在留資格での入国は少ないということが大きな特徴です。
もともと、日本国内での就労に関する在留資格は、フィリピンでは高度人材とEPAによる人材受け入れしかありませんでした。
そのため、外国人技能実習生や留学生の資格外活動によるアルバイトでその場しのぎのような労働力の確保を行ってきました。
こうした制度の歪みは前々から指摘されてきたことで、特定技能の在留資格が新たに創設されたことで、正式に労働を目的とした来日が認められるようになったということになります。
介護分野以外でのフィリピン人労働者が期待できる分野

既に実績のある介護分野以外でフィリピン人労働者が活躍できそうな特定技能の分野もあります。
特定技能1号として認定された分野には外食業と宿泊業があります。
外国人観光客を多く招待したいという政府の目的もあり、外国人労働者のこの二分野への許可は非常に大きな意味を持つものと思われます。
ホテルやレストランでも外国人の従業員を正式に雇用することが可能となり、今までのような留学生や技能実習生ではないため、労働に関する制限もありません。
また、フィリピン人は外国語として英語を早くから習得しているため、外国人観光客に対して英語でのコミュニケーションを取ることができます。
これにより、海外からの観光客の接客にもフィリピン人労働者が活躍できる場として広がっていくのではないかと考えられます。
しかし、こうした特定技能による就労はまだまだこれからの制度となり、運用上での改善なども多く出てくるのではないでしょうか。
外国人技能実習生と特定技能在留資格との違い

では、今まで馴染みの深かった外国人技能実習生と特定技能1号との違いはどのようなものがあるのでしょうか。
外国人技能実習制度は、就労という観点の在留資格でなく、どちらかと言えば技能を身に着けるための研修という位置づけのものになります。
そのため、技能実習生を管理する監理団体へ実習計画や日本語教育の計画を提出しなければなりません。
また、特定技能は就労を目的とした在留資格なのに対して、技能実習は技能を実習により身に着けるという実習が主な目的となります。
そのため、技能実習生は労働保険や年金などの就労に必要な費用を雇用時に支払わなくてよいと誤解されがちですが、実際には支払わなければなりません。
その点、特定技能の在留資格は就労に関する資格となりますので、労働保険や年金と言った労働者を雇用する際の保険にも加入することは分かりやすくなっています。
技能実習生は、3年から5年の期限付きの在留資格であり、期限を迎えた場合帰国しなければなりません。
特定技能の1号については最大5年間の期限付き在留資格であります。
その部分については共通していますが、特定技能の2号となった場合、在留資格の期限がない形になります。
その場合、ほぼ永住権と同様のものとなりますが、現在、業種が建設業と造船業に限られています。
特定技能在留資格と高度人材との違い

外国人が日本で就労する場合の最も代表的な高度人材による在留資格と特定技能の在留資格との違いはどのようなものでしょうか?
高度人材とは、高度な知識や技術を利用して日本で働くための在留資格となります。
入国の際に学歴や母国での年収などの基準があり、大学教授や技術者や医者といった日本でも高度な知識や技術を持った人が該当します。
高度人材の在留資格は条件を見ても、簡単には取得することが容易ではないものであるということは分かります。
特定技能が創設される前は、就労可能な在留資格は高度人材に関するものだけでした。そのため、外国人が日本で就労するには世界でも最も難しいとまで言われていた時代もありました。
その後に外国人技能実習生による実習に関する就労が認められるようになり、今回の特定技能の在留資格の創設につながっています。
高度人材による在留資格と特定技能2号については、更新を重ねれば日本に居続けることも可能であり、家族を日本に呼ぶことなどもできるようになり、ほぼ同等と言っていいかもしれません。
しかし、特定技能2号についてはまだ運用が始まったばかりの在留資格となりますので、今後の制度変更で詳細が変わる可能性もあります。
特定技能に関する試験を国内外で初めてフィリピンで実施

介護に関する特定資格を取得することのできる試験を国内外で初めてフィリピンで実施されたということで大きな話題になりました。
それだけフィリピン人の介護職員に期待をされているということになると考えられます。
介護分野に限らず、南国の明るい性格やホスピタリティ溢れる精神の国民性が、今後増えていくであろう宿泊業や外食業での特定技能分野で活躍していくものと思われます。
フィリピン人に限らず、特定技能の在留資格をもった外国人労働者による労働力がこれからの日本を支える時代がすぐそこまで来ています。
弊社では最低時給で雇用できる日本語堪能で優秀なフィリピン人スタッフを紹介しております。雇用、法律関係の質問から些細な疑問、質問でもお気軽にお問合せ下さい。