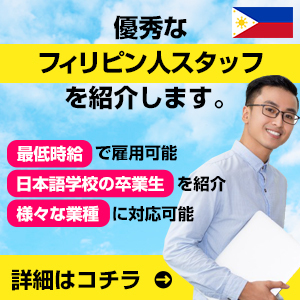農家や農業に置いても人材不足の問題は押し寄せてきております。
特に農業においては、以前から問題となっていた農業従事者の高齢化も合わせて大きな問題となっています。
農業や農家の人材不足、人手不足とそれを解消するための解決策について考えてみたいと思います。
農業に関する高齢化は1970年代から言われている
農業に関する担い手不足や高齢化と言った問題は1970年代から既に言われている話であり、今様々な業界で問題となっている人手不足とは一線を画するものとなります。
この問題は、農業や農家の事業、業界の構造上の問題ということです。
工業や商業のように新規参入が難しいのが農業の特徴です。
これは、既存の農家を守るための政策であり、つい最近まで農業を会社で行う農業法人の設立にも厳しい基準が設けられていた経緯があります。
こうした状況に置いて農家は世襲による事業継続を余儀なくされ、実家の農家を継ぐという環境が当たり前だったころによく働いていた制度でした。
そんな世襲による農家の事業継続がうまくいかなくなってきたことが1970年代から言われていたということになります。
農業の高齢化や人材不足の問題は、既存の農家を守るために問題を先送りしてきた結果であるということです。
作物のブランド化ができない農村は収入がなく厳しい

山梨のぶどうや青森のりんごなど農産物のブランド化に成功しているような地域では、農家の所得も高く、機械を使ったり多くの人を雇ったりすることが可能です。
しかし、そこまで有名な農産物を生産していないような地域では、農産物を高く売ることができないため、農業を続けても非常に厳しい生活をしなければならなくなります。
そうなってしまうと若者が農村に残ることに希望を見いだせずに都市部へ出ていってしまうといったことが起こってしまいます。
地元農協などが、生産品のブランド化に奔走しても人口の流出が止まらないという悪循環に陥ってしまうというのが多くの農村が置かれている状況です。
農業では、高齢化、人口減少に合わせて人材不足の三重苦

もともと規制により、多くの制約があり、新しいことを行いたいと思ってもなかなかできないというのが農業の昔からの流れでした。
そんな環境下で、新しいことに挑戦したいという若者が農業から離れていってしまい、都市部へと流れていってしまったことにより高齢化と人口減少が、他の事業より先行して発生していました。
そこに来て、他の業界でもいよいよ人手不足が深刻となってきてしまい、農業に従事する人の募集に人が集まらないというような状況に置かれているというのが現状です。
日本の農業は規制で守られている?
日本の農業は規制で守られているということがよく話題となりますが、農業に従事して、作物を育てるプロが今も農家だというように勘違いしている人が多いと感じます。
そういった農業の知識も重要ですが、流通経路の確立なども大きな課題です。
今まで個人で農家をやってきた人にとって、流通経路の確率は農協や卸売り市場の仕事でした。取れた作物を市場や農協に出荷するだけで、後のことはやってくれるということでした。
しかし、農業法人や流通を自分で確立したいと考えている農家の人にとって、農業を行うこととは別の課題として、自分の商品をどんな人に買ってもらうかという部分がうまくいかずに、農業を辞めてしまうという人も多いというのが実情です。
農業を行っている人もブランディングやマーケテイングにより、自分たちの農産物を買ってもらう人も考えるという商業の知識も必要となるのがこれからの農業であると感じます。
確かに規制は厳しいですが、こうした農業に従事する際の必要なスキルが変わってきているために、農業が難しい事業となってきてしまっているということも人手不足の大きな原因とも言えます。
人材不足を解消するための方策

多くの課題を抱え、改革期に入っているとも言える日本の農業ですが、人材不足の状況は変わりません。
そういった状況下では、多くの人手を必要としてもなかなか人が集まりません。
そこで、外国人技能実習生の活用が挙げられます。
外国人技能実習制度では、制度開始当初から、農業への技能実習制度の適用が許可されています。
実際に農業分野では多くの外国人技能実習生が、現場で働いています。
外国人技能実習生は、農協なども申請を行っている農業関連の監理団体より派遣されます。現場で日本語と農作業を行うことで実習を行います。
農業関連の技能実習生は問題となっているケースも多い
農業関連の技能実習では、問題となるケースが多いと言われています。
その一つの理由として、農業は残業に関する協定の適用除外となっていたためです。
農業や畜産業は、自然相手のため、労働基準法で規定されている労働時間や休憩、週休といったものが適用除外となっておりました。
外国人技能実習生においては、農業分野に置いても適用されるものになっているのですが、実際に従業員が働いているのに、実習生だけ休むというわけにはいかないことが多いためです。
こうした状況から農業分野では実習生の長時間労働などの問題が起こりやすく、農業分野に置いては、厚労省や農水省なども監視を強化しておりました。
農業関連の技能実習制度はこうした制度の誤解などにより、問題となるケースが多いです。
農作物のニーズをつかんで、働き手もつかむ
農作物の流通経路の確立は、農協や市場、商社などで行ってきたものを、農家や農業法人が行うというものですが、そういった部分を自分で確立できると利幅も大きく取ることもができ、生活にも余裕が生まれます。
今までは、こうした部分を農家の人たちが人に任せてしまっていたため、安く買われるなどの状況が発生してしまい、事業が思うように伸びていきませんでした。
衰退が続く農業に、外国人技能実習生の力を借りて、農業の巻き返しを図るというのも一つの手でしょう。
弊社では最低時給で雇用できる日本語堪能で優秀なフィリピン人スタッフを紹介しております。雇用、法律関係の質問から些細な疑問、質問でもお気軽にお問合せ下さい。