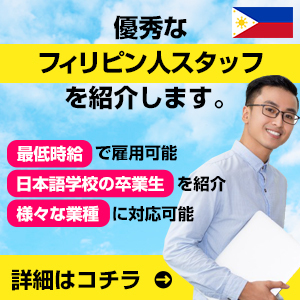現在の日本は、とにかく人手が足りません。景気がよくなっているということも相まっているのですが、様々なことを行いたいという需要に対して、供給側である労働力が足りないというのが現状です。
その状況が顕著に表れているのが、建設業、土木業界と言えます。
建設、土木業は、高度経済成長期から日本の屋台骨を支える業界として、日本経済に影響力を及ぼしてきました。
しかし、バブル崩壊後の長期的な不況はこの業界をボロボロにしたと言っても過言ではありません。
そんな建設、土木業界の人材不足の現状、原因と解消するための解決策について、考えていきたいと思います。
建設、土木業が最も栄えた高度経済成長期
第二次世界大戦が1945年に終わり、日本は焼け野原になりました。
昭和30年代には終戦からの復興や池田内閣の所得倍増計画による公共投資の増大に合わせて、建設工事や土木工事が政府や地方公共団体からの発注により、大きく成長しました。
この時は、日本の景気自体もよかったということもありましたが、日本道路公団の新設などにより、高速道路の建設が始まり、土木工事においても多くの大型発注があり、まさに我が世の春という状況が長く続きました。
また、1964年に行われた東京オリンピックの建設需要などもあり、多くの公共建設工事が発注されました。
現在も東京オリンピックの開催を控えており、建設業界は同じ状況なのでは?と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、その当時と大きく異なるものがあります。
高度経済成長期を経て、業界規模が大きくなるも失速

大型受注を繰り返してきた建設業界の代表的な会社は、その都度、人員の増強、設備投資を繰り返し、会社の規模を大きくしてきました。
それは同時に常に前年を上回る需要に応えなければならないということを意味しておりました。
そうでなければ、大型の建設工事や土木工事を受注、工事の竣工を行うことができません。いつしか建設工事が一段落すると、それでも多くの供給を行わなければならないという業界の使命を遂行しなけれなりません。
東京オリンピックが終わると、公共投資により景気を良くするという考え方が根付くようになってきます。地方の美術館、競技場などの箱ものと呼ばれる公共工事が多く発注されました。
それらの多くは人口の割合に対して、過剰なものも多く含まれていたことは明らかです。こうした需要に応えることで建設、土木業界はその体制を維持することができていました。
80年代に入ると、バブル経済の影響を受け、内需拡大という命題が出ます。景気をよくするために、国内の需要を大きくするというものです。需要を無理やり作ると言っても過言ではありません。それを供給側である建設業者と政府などが結託して行っていました。
この時ほど無駄な公共工事が多く発注されたことはないでしょう。多くは負の遺産として修繕費の捻出に苦慮しています。
バブル経済が弾けると、公共工事の発注は一気に減り、民間のマンションなどの建設もストップした建設業界の暗黒時代が訪れます。
会社の規模を大きくし続けた結果の突然の工事激減に多くの会社が倒産、廃業を余儀なくされます。
建設、土木業界が今までのやり方にNOを突き付けられた瞬間でもあります。
減りゆく税収に公共工事の発注価格も低下

公共工事は、政府や地方自治体の税金により発注され、多くの地方自治体はバブル崩壊後、税収の落ち込みに苦慮することになります。
今まで無理をして発注した工事の発注代金を負債として持つ自治体も多く、新規の公共工事は必要なものに限られます。
また、お金がないということは、一つの工事にかけられる価格もなくなることを意味します。発注価格の低下が起こるようになりました。
また、今まで多くの工事があったため、持ち回りで入札を行うことも談合として大きく批判されました。今までは多くの工事があったため、談合などを行い、皆で協力して工事を回すということが発注価格を吊り上げるということで禁止されました。
これにより、工事は安い価格を掲示した会社が受注していくようになります。
業界全体でリストラを余儀なくされる

どんどんと追い詰められていくこの業界に対して、大きくなりすぎた組織はなすすべもありません。
仕事がないのですから、多くの従業員に希望退職などを推奨し、リストラを行いました。これは、大手企業だけでなく中小企業などでも同様です。
業界全体での就労人口自体を減らしたと言ってもいいでしょう。その際に問題だったのは、バブル崩壊後に入社した若年層ではなく、給与の高い中高年層だったということです。
仕事のスキルや技術が身に着いてきて、いくつもの難工事を竣工させてきたようなベテラン勢から固定費の削減ということで、リストラを進めてきました。
その結果、この業界はリストラや仕事が減ったというイメージがついてしまい、建設、土木業を志望する若者が減ることになってしまいました。
そこに来ての東京オリンピックの開催

ここにきて、2020年に東京オリンピックの開催が決まりました。
開催が決まった当時こそ明るいニュースとして希望を持たれましたが、実際には税収は変化がないものの、国や地方の借金が多く、とてもオリンピックの開催ができる状態なのかということが問題となりました。
当時の東京都が提案したものもコンパクトなオリンピック、既存の設備を使えるところで開催するなど資金をかけないオリンピックというものを提案し、それが認められたというものでした。
そのため、開会式会場などの建設工事の発注価格が安すぎて、工事ができる建設会社がいないなどという事態にも陥りました。
工事価格が安いということは、悪い条件を呑まなければならないという事になります。しかし、こうした安い工事であってもオリンピックのための道路整備などの土木工事なども仕事がないよりはいいということで引き受ける会社も多くなります。
しかし、リストラを進めた結果、こうした建設工事の需要に応えるための人材が確保できないなどの非常事態に陥ってしまいました。
さらに、バブル崩壊後に中高年層をリストラしたため、技術を持った建設、土木技術者が少なく、技術の継承ができていないなどの問題も抱えています。
1964年に開催された東京オリンピックの当時と比べると、暗い話題の方が多いという印象です。
特に人手不足はとても深刻です。技術者は一朝一夕で育つものではありません。業界人口が縮小したまま、需要だけが増えてしまったため、他の業界にはないほどの深刻な人手不足となってしまったということです。
そこで、外国人労働者の活用を考える
こうした建設、土木業界全体が抱える問題と、人手不足に現在の特効薬とも言えるものが外国人労働者の活用です。
外国人技能実習生制度では、建設や土木への技能実習生の受け入れを許可しています。
適切な外国人技能実習生の監理団体より各企業へ派遣される外国人技能実習生は、よく働き、現在の人手不足の業界において頼りになる存在です。
元々の外国人技能実習制度であれば、日本で働ける期間は3年ですが、新制度となり一定の条件を満たした場合、5年まで働くことができるような制度となりました。
5年間と言えば、もう職場の主力として働いているような頃です。
外国人技能実習生に頼らざるを得ない建設、土木業界

外国人技能実習の期間が新制度より延長になったことで、オリンピックの建設ラッシュを乗り切ろうというということが狙いです。
丁度5年であれば、東京オリンピックは開催されます。その間の建設需要は、外国人労働者によって乗り切るという事が業界内の常識となっています。
東京オリンピックが終われば、また以前と同じような安い工事を請け負い、数少ない工事を取り合うような状況となることは目に見えています。
オリンピックなどの国際イベントが行われると、一時的な建設工事ラッシュが起きますが、開催が終わってしまうと建設工事などが今までと同じ水準まで落ち込んでしまいます。目の前の繁忙期を取りあえず回せばいいと考えているものと思われます。
その後の建設工事需要の増加といった長期的な見通しはオリンピックの時ほどいいものではないからです。
外国人技能実習生との信頼関係が重要
いくら安い工事が多くなり、数が減ってきて人や金額を減らさなければならないとしても、手抜き工事などの不正行為は大きな社会問題となります。
マンションのくい打ち偽装など、工事金額、工事期間が少ないために起こした手抜きは大きな代償を払うことになります。
金額が安くても品質を下げることができないのが建設工事の難しいところです。
そうなると人件費などの関係で一人当たりの金額の安い外国人技能実習生に頼るというところも出てきますが、ただ言われたように働かせばよいということができないのが建設工事の難しいところです。
日々変わる建設現場では、危険な個所は何か所も多く、日々変わります。
死亡事故などを起こしてしまえば、発注元との信用問題にもなります。
こうした危険な個所から守るということも建設工事を行う人達の義務でもあります。そのためには、外国人技能実習生との信頼関係がもっとも重要なものになってきます。
忙しい時期であっても、様々な工事を回さなければならないということで、連携を取る場合には技術レベルや仕事ができるなどよりも信頼関係が重要となります。
外国人との信頼関係を作るには?
日本人との信頼関係を作るのもなかなか難しいものですが、外国人との信頼関係を作るにはどのようにしたらいいのでしょうか?
まずは、相手の文化を知るという事から始めてみましょう。
日本人だけのコミュニティで過ごしてきた人は特にそうですが、「普通こうだ」という固定観念を知らないうちに持ってしまっています。
仕事においてもこれだけ伝えておけば、あとはやってくれるというものを持ってしまっており、日本人から見ると異文化でもある外国人の考え方が理解できないということで、うまくいかなくなってしまうことも少なくありません。
短所ばかりで長所のない人は存在しません。こういうものは苦手だけど、こっちは結構できそうだというものが見つかれば、そちらを伸ばしていくなどを行い、少しづつ育成していくことも可能です。
その人のバックグラウンドを理解して、長所を伸ばすような教育を行っていけば数年後には一人前になっているのではと思います。
工事価格の低下を人材の活用で乗り切る
他の業界でも言われていることですが、建設、土木業界でも全体需要の減少は避けられないものです。
そこで、まずは人材の活用方法を検討しましょう。その際にまず外国人技能実習生の活用というものがあります。外国人でもきちんと教育を行えば一人前になります。
政府の後押しもあり、人材不足の現場でも外国人を活用していくことができます。
他の業界にない大きなリストラを経験している建設、土木業界では人材不足の解決は喫緊の課題です。
外国人技能実習生は、そんなあなたの会社の主力となってくれるでしょう。
弊社では最低時給で雇用できる日本語堪能で優秀なフィリピン人スタッフを紹介しております。雇用、法律関係の質問から些細な疑問、質問でもお気軽にお問合せ下さい。