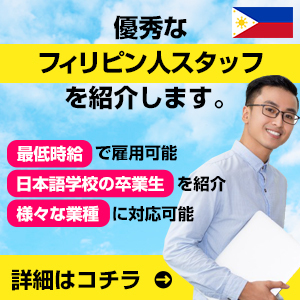外国人技能実習制度は様々な業種で受け入れられており、その有用性が証明されていることはよく知られています。
では、東京オリンピックの開催や道路など高度成長期に建てられた建造物の老朽化対策などで人手不足となっている建設業、土木業での受け入れは可能なのでしょうか?
建設、土木業で受け入れ可能な職種
厚生労働省の外国人技能実習制度に関する法律で、建設、土木に関する受け入れ可能な職種は細かく決められており、その種類は22職種33作業となっております。(平成30年4月現在)
建設関連では、左官、建築大工、内装仕上げ施工、サッシ施工、防水施工など様々な職種において行える作業の一つ一つが決められています。
土木関連でも同様に、さく井、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工などとなります。
これらの職種において、外国人技能実習生が必ず実習として行う作業、それに付随する作業、使用する材料、機器などが決められております。
外国人技能実習生は、原則として現場作業はこの職種以外のものは行うことができません。
また、この業種に指定されていても、外国人技能実習生を受け入れ時に提出する実習計画書に業種の記載がなければ、作業を行うことができません。
基本的に何でもこなすような一般建設土木業者で、実習生を受け入れていても、実習計画によっては行うことができない作業も出てきてしまいます。
土木業ではこんな例も過去に
土木業では、東日本大震災での福島第一原発事故による福島県内の除染作業を請け負っている会社もありました。
外国人技能実習制度は土木業でも受け入れが可能ということで、外国人技能実習生に福島県内の土木工事の現場作業として除染作業を行わせていた実態が新聞報道などで明らかになりました。
これを受けて、厚生労働省は文書による注意喚起を出す事態に発展しました。
この中で、除染作業は海外でも同様の作業は行われていない、被爆対策などが必要で技能習得に専念できる環境ではないとの理由より、除染作業への技能実習生の受け入れは不可という回答を行っています。
また、この事態を受けて、実習計画認定時にこうした業種への従事を行わせない旨を記した誓約書の提出を求められるようになりました。
土木、建設業は職種が多岐に渡る
土木、建設業は、他の業種と比べても職種が多岐に渡り、各職種の専門職人による分担により成り立っています。
ゼネコンなどの総合建設業では、社員として専門の人を雇わず、その業種を専門に行うような土木、建設業者に部分的に外注を行い、その業務状況を管理することで多くの仕事がある建設工事をマネジメントしています。
ある特定の分野に特化した土木、建設業を行う企業であれば、その職種が外国人技能実習制度にあった場合、実習生の受け入れを行うことが可能です。
総合建設業として、現場監理を行う場合でも、監理技術者としての需要が海外でもあることから、実習の対象となるため、外国人技能実習生の受け入れが可能です。
これは、建設業や設備工事業での「管理、補助的経済活動を行う事業所」への実習が認められていることによります。
それでも職種に例外が出てくるのが土木、建設業
これだけ多くの職種があるにも関わらず、それでも例外の職種が出てくるのは、土木、建設業です。
それだけ、工事現場の施工は多岐に渡り、法律による規定がし切れていないのが現状です。そのため、除染事業に外国人技能実習生が派遣されて問題になるケースなど様々な例外が出てきます。
また、施工方法などに新技術が使われた場合、外国人技能実習生にも経験させたいと考えてもその職種に当てはまるものなのか、職種を超えたものなのかを注意してみなければなりません。
例えば、施工の効率化で職種の枠を超えたような施工方法が出てきた場合、一つの職種しか届け出をしていない受け入れ企業であれば、その施工方法では外国人技能実習生に実習させることができないような事例も出てきます。
これはゼネコンなどの工事の元請企業が指定する場合もあり、実習生の受け入れ企業で決めることができないケースもあり、難しいところです。
こうした製造業や他の業種と違って、建設現場によって臨機応変な対応が求められる土木、建設業ではこれ以外にも多くの問題が出ています。
多重下請けが当たり前の建設業界
先ほどゼネコンなどの総合建設業では、専門分野の職種を外注により管理するというように述べました。
ここから、建設工事では一つの会社で工事を行うのではなく、多くの会社が元請工事会社を頂点としたピラミッドのような多重下請け構造が形成されます。
そのため、元請会社から一次下請けまでは発注形態などを見られることが多いですが、その下の部分まではなかなか目が届かないケースも多くあります。
これを悪用して、実際に外国人技能実習生が雇用される会社に発注されるまでに多くの中間会社(ブローカー)が入り、マージンを搾取するようなケースも見られていました。
こうした建設工事でブローカーのような実態のない会社が発注に関わることは、丸投げ行為にあたり、建設業法でも禁止されています。
しかし、発注に関わらないまでにも、仕事を紹介する代わりに紹介料を要求するようなケースもあります。
建設業界でも下請け発注の適正化に取り組んでいますが、実態を把握することが難しく、なかなか改善に至っていないケースが多いようです。
その場合、発注単価の減少などの実害を受けるのは外国人技能実習生などを雇用する場合が多い小さな会社です。
こうした状況は外国人技能実習生の賃金低下などにもつながるため、業界全体で改善に取り組んでいかなければなりません。
弊社では最低時給で雇用できる日本語堪能で優秀なフィリピン人スタッフを紹介しております。雇用、法律関係の質問から些細な疑問、質問でもお気軽にお問合せ下さい。