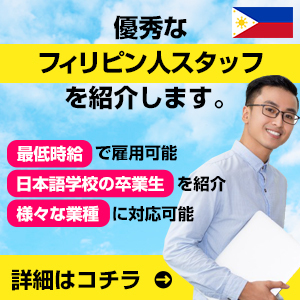外国人技能生を雇用しても、業績の悪化や受注量の減少など想定外のことが起こり、社員を減らさなければ会社が存続できないという状況に追い込まれてしまうこともあるかもしれません。
そんな危機的な状況であっても、外国人技能実習生を雇用している経営者は解雇をすることは可能なのでしょうか?
経営者が従業員を解雇できる場合
経営者が従業員を解雇、つまりクビにするということは、簡単にできるのでしょうか?
まずは日本人の場合について考えます。
経営者に雇用されている従業員は労働基準法で守られています。
これはアルバイトやパートタイマー、派遣社員などについても同様です。
経営者が様々な理由で解雇をしたいと考えても、従業員がそれを不服とすれば、経営者に対して解雇権の濫用を申し出ることができます。
つまり解雇の基準に満たないのに解雇されたことはおかしい、というように経営者に対して異議申し立てを行うことができます。
こうした解雇に関する裁判は多くのケースで行われており、経営者の認識と従業員の認識が一致しなければ裁判に至るということになります。
経営者が会社の経営が厳しいということで解雇したいと考え点も、従業員としても給与収入などの生活がかかっています。
この二つの関係がおかしくなる場合が解雇時ということと言えるでしょう。
現実的には希望退職者を募集する

米系の外資系企業などでは整理解雇などが頻繁に行われていて、従業員側もそれに慣れているため、次の転職先を探すということもよく聞きます。
しかし、日系企業の特に大手企業ではそのような対応を行うと、労働組合などから解雇権の濫用ということで糾弾されてしまいます。
経営的に行き詰ってしまった場合、退職金を上乗せして、対象年齢の従業員に自分から辞めてもらうように促す希望退職者の募集ということが日系企業で一般的に行われている整理解雇であるといえるでしょう。
その場合のデメリットは、退職金費用が必要以上にかさむ、辞めてほしくない人に辞められてしまうということが挙げられます。
こうした対応をしなければならないほど、日本の従業員は守られていて、解雇を行いづらいということが言えます。
労働基準法に記載されている「解雇事由」

ただし、経営者がいくら解雇できないといってもその基準を満たせば解雇を行うことが可能です。
解雇を行う際の大前提として、客観的に見て合理的な理由があるということと、社会通念上相当であると認められないと解雇を行うことができないというものがあります。
極めてあいまいな基準ですが、誰がどう見てもこの人は解雇するぐらいに勤務態度が悪い、会社の経営が、経営者の努力でカバーしきれないほどの業績悪化があり、会社を継続させていくには従業員を減らすしかないという状況でない限りは、解雇を行うことができないということになります。
しかし、こうした状況での解雇を従業員が受け入れなかった場合、裁判所などの判断が必要になります。その場合、「誰がどう見ても」の部分を証明するための記録が必要となってきます。
ボイスレコーダーや、メールの内容など、この記録を残すことは非常に労力を伴います。
またその基準が他の人が見ると、勤務態度の悪さは指導でなんとかできるレベルかどうかの基準も客観的にみて判断されます。
そこは経営者が何をやっても駄目だと思い込んでいても、他の人が見ると違うかもしれません。
解雇に関する裁判は、よほど強力な証拠がないと、どちらが勝つかわからないものになります。
横領や不正行為などの懲戒解雇を不当とする場合などは、経営者側が極めて有利となります。解雇に関する裁判はこうした場合でない限り行わないほうが得策ではないかと考えます。
外国人技能実習生においても日本人と同じ「従業員」となる

では、本題でもある外国人技能実習生の解雇に関して考えてみましょう。
外国人技能実習生であっても、日本人と同じ労働基準法が適用されるということを過去記事でも解説してきました。
解雇に関する事項についても、外国人技能実習生であっても日本人と同じように労働基準法が適用され、解雇事由には客観的に見て合理的な理由が求められます。
例としては、会社の経営難になったからということで、外国人技能実習生のみを実習期間前に先に解雇し、日本人従業員を残すということについても不当解雇になります。
技能実習生に関する解雇のニュースは、各地で取り上げられており、特に実習期間が満了していない状態での解雇は大きな社会問題となっています。
企業の業績が悪化した場合に解雇されるということは、日本人であっても状況は同じですが、外国人技能実習生の解雇については、「外国人差別」を取り上げられやすく、個人加入が可能な労働組合に加入して、受け入れ企業と争うというケースも出てきています。
外国人技能実習生であっても、他の日本人と同様に、労働組合に加入する権利を持っているため、こうした機関から受け入れ企業に不当解雇であるという通知が行くことになるかもしれません。
また、昨今、差別やハラスメントに対する世間の目が厳しくなっていており、正当な理由がなく、外国人技能実習生だけを解雇すれば、外国人差別ではないかと糾弾されてしまいます。
事業が思うようにいかなくなった場合は、監理団体へ相談

現在、外国人技能実習生を受け入れることができる企業は、黒字決算を行っている会社のみに限られています。
これは業績不振による解雇を防止するためのものでもありますが、経営が安定している企業でなければ、技能実習を継続的に行うことができないということの判断の基準であると考えられます。
しかし、どうしても事業が思うように伸びない、経営が想定外に悪化してきたということが出てきてしまうということはあり得ます。
こうした場合は、監理団体へ実習先の変更を申し出る事ができます。
外国人技能実習生にとっては、実習先である受け入れ企業が変更となってしまうことになりますが、どうしてもそういった状況に追い込まれてしまうということは、企業運営の中では出てきます。
その場合は、まずは技能実習生の納得を得るということがとても重要なプロセスになります。
これは他の日本人従業員の解雇や配置転換などと同じように、外国人技能実習生の理解があるかないかでその後の対応は大きく変わってきます。
さらに外国人技能実習生を雇用する際に、国に監理団体を通じて実習計画を届け出ております。
こうした手続き変更なども行う必要があります。実習計画を途中でやめるのですから、相当な理由が必要になります。
こうした中で、企業利益の利幅を上げることが目的だったことが発覚する、ただ単にワンマン経営の「首切り」のような状況と感じられた場合、不当解雇であるということで報道機関を通じて糾弾されたり、裁判に発展する可能性もあります。
企業都合の解雇だけでなく、勤務態度が悪い、言われたことをやらないなどの勤務態度の問題などで解雇をしたいと考えた場合は、日本人の労働者と同様に客観的に見て相当と判断されなければ解雇を行えません。
しかし、外国人技能実習生は母国での語学研修などの費用を借金して来日していることも多いため、必死に働くということが根底にありますので心配することは少ないでしょう。
どうしても個人の問題で外国人技能実習生が働かないなどの問題があった場合は監理団体と協議して今後の方針を決めるようにしましょう。
人材不足の中で、外国人技能実習生の労働者としての権利も高まっている

外国人技能実習制度の歴史の中で、不当な扱いが大きく問題となり、制度の変更を繰り返しながら、発展してきたということが挙げられます。
入管法の改正もあり、特定技能の在留資格が創設されたこともあり、外国人技能実習生を含めて、外国人労働者に人手不足の解消を期待していることが分かります。
それと同時に、外国人技能実習生の労働者としての権利が日本人と同等であるということも経営者の意識の中で変わっていかなければならないことでもあると言えます。
今までの外国人技能実習生が都合のいい使われ方をして、経営が少し悪くなったら、解雇するというような身勝手な雇用では、日本人はもちろんのこと、外国人技能実習生も寄り付かなくなってしまいます。
日本人が人材不足で労働者の権利が高まっているのと同様に、外国人技能実習生の労働者としての権利も高まっているということが言えます。
働きやすい職場は優秀な人材が集まりやすいということはよく言われていますが、それには経営者が従業員を会社に必要なものとして、将来の業績向上の投資として人件費をかけるという姿勢が求められます。
弊社では最低時給で雇用できる日本語堪能で優秀なフィリピン人スタッフを紹介しております。雇用、法律関係の質問から些細な疑問、質問でもお気軽にお問合せ下さい。