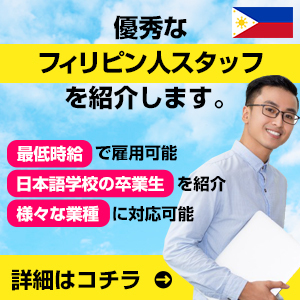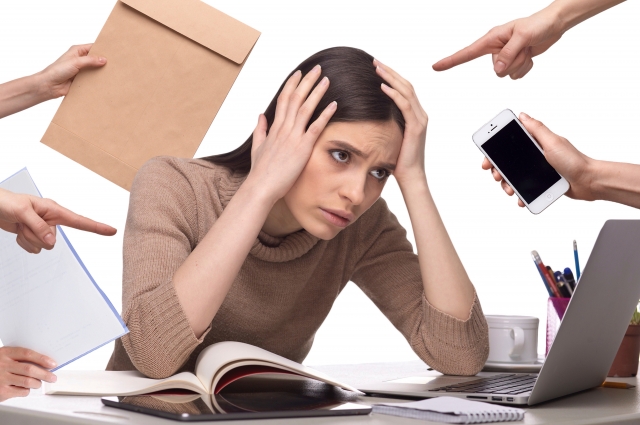外国人技能実習制度は、昨年国会でも入国管理法の改正案が注目されるなど国内での関心も、数年前と比べても高まっています。
国会でも外国人技能実習生の処遇が議論され、制度自体名前は聞いたことがあるという人も多くなったと思います。
今回は復習の意味も兼ねて、外国人技能実習制度の仕組みと雇用までの流れももう一度おさらいしてみます。
外国人技能実習制度とは?
まずは、外国人技能実習制度とは具体的にはどのような制度なのかをもう一度確認しておきましょう。
外国人技能実習制度は、技能実習法で定められた制度で、日本で培われた技術や技能を、発展途上国から来日した技能実習生に実務を通して教えるという制度です。
技能実習という名前からも、実務の習得が目的であり、期間も設定された有期雇用となります。
これは、1960年代に日系企業の海外の現地法人などから社員教育として来日して研修を受けて現地法人で、技能を役立てる研修を行っていたことが高く評価されたことが原型となります。
そのため、日本で技能実習を一定期間行ってから、母国に帰って日本で働いて学んだ技能を活かしてもらうことを目的としているため、有期雇用となります。
様々な分野で働いている外国人技能実習生は、母国に帰ってその技能を活かして母国の発展に役立ってもらうという大きな政府の期待があります。
外国人技能実習制度は、技能実習生を通して、発展途上国の発展に寄与する国際貢献が最終目的となっています。
外国人技能実習制度の雇用までの主な流れ

外国人技能実習制度の雇用までの流れは主に二つの種類があります。
一つは現地での採用から日本へ来るための手続き、雇用に関してまで一元的に単一企業が行う単独企業型です。
これは1960年代に行われていた日系企業の現地法人からの研修での来日を行ったことの流れをそのまま残したものとなります。
この場合、技能実習生も日本に行く前から働く会社が決まっており、実習生も安心して来日することができます。
しかし、現地での採用から来日の手続きまで単一企業で行うため、費用面ではどうしても高くなってしまうというのがデメリットとなります。
実際に単独企業型で受け入れられている外国人技能実習生は、実習生全体の5%以下となっています。
外国人技能実習生の母国に海外支店があるような大企業でなければこうした形で実習生を募ることができないためこのような結果となっているものと考えられます。
外国人技能実習生の受け入れを行っている多くの企業は中小企業で、大規模な募集を行うことができないという現状があります。
そんな中小企業のために外国人技能実習生を一括で派遣、労務管理を行う方式が団体監理型の受け入れ方式となります。
外国人技能実習生の母国に、日本語教育や基礎的な技能教育を行う機関として「送り出し機関」があります。日本国内では農協や製造組合といった財団法人などの公共機関が日本国内の「監理団体」となってこの二つの機関が契約を行い、監理団体から日本国内の関連する中小企業へ外国人技能実習生を派遣するという方式が「団体監理型」となります。
現在、外国人技能実習生はこの団体監理型で、各地の企業に派遣され活躍しています。
この方式のメリットとしては、単独企業型と比べるとスケールメリットにより、技能実習生を採用する際のコストを安くすることができるというものが非常に大きくなります。
このため、多くの中小企業の人手不足に対応し、外国人技能実習生に活躍してもらう大きなきっかけになりました。
母国での外国人技能実習生

母国では外国人技能実習生は送り出し機関での公募に応募し、日本語教育を受ける訓練を一定期間行います。その後、ビザの発給や来日の準備をします。
外国人技能実習生が団体監理型により、多くの中小企業に採用されていますが、現在、現地企が送り出し機関となっていることが多く、以前はブローカーのような会社も存在していたことが大きな問題となっていました。
そのため、日本に来るまでの教育が十分にされておらず、実習生本人が困ってしまうといったことがよく起こっていました。
今後、技能実習法の強化により、送り出し機関は、母国の政府公認の機関からのみの受け入れとなります。
送り出し機関は外国にあるため、日本国内の法律で取り締まることができません。今まで異常な低コストで外国人技能実習生を採用していたような送り出し機関は、こうした法の目をかいくぐって違法な採用活動を行ってきたと言ってもいいでしょう。
違法な技能実習生の採用活動は、今後厳罰化に向かうと考えられますので、今後の動向や法改正にも注意が必要です。
来日後の外国人技能実習生

日本に来日した外国人技能実習生は、監理団体の方針で派遣される企業の面接などを受けます。
監理団体は加盟する農業法人や工場を持つ企業など、多くの業種で公的な立場となる協同組合などがその役割を持ちます。
場合によっては、そういった組合から認可を受けた企業などが監理団体となることもあります。
監理団体の役割は企業に派遣後も、在留資格の監理や日本語教育の進捗管理、派遣先の企業が実習計画書以外の仕事をさせていないかなど、外国人技能実習生の国内での管理を行います。
しかし、技能実習生は派遣された企業に雇用され、給与も派遣先企業から出ます。監理団体は実務ではなく、派遣先企業が違法な労働をさせていないか監理をする役割も持っています。
入管法の改正で、実習期間の延長する業種が決定

今まで、外国人技能実習生の実習期間は、業種によっても異なりますが、最長でも5年でした。
昨年11月の国会で、入管法の改正が承認されたため、技能実習生の実習期間は最長10年まで行えるようになります。
技能実習生とはいえ、10年も日本国内で働けば、その企業にとってはなくてはならない戦力になることが想像できます。
国会で野党が入管法の改正は実質の移民受け入れだと批判したのはその部分にあります。
10年間真面目に働けば、多くの方法を用いて日本国籍を取ることもできるようになるかもしれません。
外国人技能実習生であっても、日本国内で労働保険や税金を納めるため、真面目に働いたのであれば、そのような道も用意してあげてもよい気がします。
外国人技能実習生が都合のいい制度にならないために

今回の入管法の改正により、労働力を発展途上国の外国人に頼るということが正式に決まったという見方もできます。
最長で10年も日本で働くのに、実習期間が終わったから母国へ帰ってもそれに応じた仕事があるかどうかは不明瞭です。
今までの外国人技能実習制度では、日本人にとっては非常に都合のよい制度となっていましたが、こうしたことを続けていては、現在、技能実習生の多いベトナムや中国も経済発展が著しく、日本に技能実習に来る外国人が来なくなってしまうという状況に陥ってしまうかもしれません。
そのため、政府も違法な機関の取り締まり強化と合わせて、実習期間の延長を決めています。
日本の企業も外国人技能実習生を上手く活用することで利益を生み出すことができるような社会になっていくのも時間の問題なのかもしれません。
それは、今までのように過酷な労働環境で使い捨てのような状態で働かされていた外国人技能実習生から、労働法を守って、生き生きと働いてもらった方が企業イメージも上がり、ひいては外国人技能実習生の国内でのイメージも上がることになります。
弊社では最低時給で雇用できる日本語堪能で優秀なフィリピン人スタッフを紹介しております。雇用、法律関係の質問から些細な疑問、質問でもお気軽にお問合せ下さい。